ナミセキセイ
オオガタセキセイ
高級セキセイ : ハルクイン系、オパーリン系
[性質]
羽の色が美しく、よく鳴き、また雛のうちから育てて手乗りにしたり、言葉を真似たりします。
水浴びはあまり好まないので、時々霧吹きで水をかける程度でいいです。
産卵 : 毎日あるいは一日おきに4~6個の卵を産みます。
抱卵(卵を温める)期間 : 17~18日くらいで、卵がふ化します。
ほとんどはメスが卵を抱き、オスはメスに餌を運びます。
巣立ち : ヒナはおよそ30日ほどで、自分で餌を食べられるようになります。
手乗りにする場合は、ふ化後約1週間くらいで親鳥から離して人工保育すると、とてもよく慣れます。
[餌]
主食 : 配合飼料(ヒエ、アワ、キビ)、小鳥用のペレット
副食 : 青菜(小松菜、白菜、ハコベ)、ボレー粉、イカの甲、塩土
発情期(卵を産む前)と、ヒナを育てている時はアワ玉を与えます。
成長期の小鳥には栄養が良好なパウダータイプのものもあります。
[飼い方]
必要なもの
鳥カゴ : セキセイインコはくちばしの力が強いので、金カゴが適しています。繁殖させる場合は巣箱が入る大きさのカゴを用意しましょう。
餌入れ、水入れ、菜さし、ボレー粉入れ
巣箱(木製) : 卵を産んでしまうことがありますので、産ませたくない場合は入れない方がいいでしょう。
遊び道具 : ブランコ、スズ、カガミなどを入れると喜びます。
[オスとメスの見分け方]
ヒナや高級セキセイでは見分けがしにくいことがあります。
くちばしのつけ根(ロウ膜)の色
オス…青色
メ ス…ピンク色
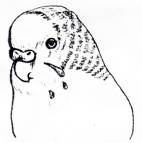
ジュウシマツ(十姉妹)
キンパラ科(フィンチ類)。古くから飼われており、原種ははっきりしていませんが、東南アジアに分布するカエデチョウ科のコシジロキンパラとキンパラの雑種といわれています。日本に初めて輸入されたのは江戸時代で、その後改良され様々な品種ができました。「ジュウシマツ」は漢字で「十姉妹」と書きますが、これはたくさんの十姉妹を一緒のカゴで飼っても、ケンカせず仲良くしていることより付けられたといわれています。
[種類]
ナミ(並)ジュウシマツ
コブチ(小斑)ジュウシマツ
シロ(白)ジュウシマツ
ミケ(三毛)ジュウシマツ
ボンテン(梵天)ジュウシマツ
[性質]
性格はとても温順で、他の鳥とケンカをすることはあまりありません。
ジュウシマツは巣の中で眠るので、必ずワラ製のつぼ巣を入れてあげます。巣引きする時もこの巣を使います。
丈夫で比較的寒さにも強い鳥です。
産卵 : 毎日1個ずつ4~5個くらい卵を産み、卵をあたため始めます。
卵をあたため始めても、産卵することがあるので、同じ日に全部の卵がかえるとは限りません。
抱卵(卵をあたためる)期間 : 14日くらいでふ化します。
ふ化したばかりのヒナは目も開いていませんが、1週間くらいすると目が開きます。
巣立ち : ヒナはふ化後20日(3週間)ほどで巣立ちます。
巣立ち後もしばらくは、親鳥からも餌をもらうので、親鳥からもらわずに自分で食べられるようになってから(2週間くらい)、親から離します。
[餌]
主食 : 配合飼料(ヒエ、アワ、キビ)
副食 : 青菜(小松菜、白菜、ハコベ)…アクの強いものはダメ。ボレー粉。
[飼い方]
必要なもの
鳥カゴ : 庭籠(にわこ)、金カゴ
ジュウシマツは数羽を一緒のカゴで飼っても、ケンカをしないので大丈夫ですが、その場合は大きめのカゴを用意しましょう。
餌入れ、水入れ、菜さし、ボレー粉入れ
水浴用の容器(瀬戸物製の小判型容器)
つぼ巣(ワラ製)
[オスとメスの見分け方]
動作と鳴声で見分けます。
動作
オス…尾を立てて体を敏しょうに動かします。
メス…尾はあまり立てず、動きもあまり敏しょうでない。
鳴声
オス…尾を立てて体を左右にふりながら “ピィリリ、ピィリリ”と、かん高い声で鳴きます。
メ ス…“ジュルル、ジュルル”と、低い声で鳴きます。
ブンチョウ(文鳥)
フィンチ類 キンパラ科。原産地はジャワ、スマトラ、ボルネオなどで、日本のスズメのように普通にみられる鳥です。日本に輸入されたのは徳川時代の初期といわれており、一般に飼われるようになったのは明治になってからだといわれています。洋鳥の中でも比較的歴史の古い鳥です。
[種類]
ナミ(並)ブンチョウ
シロ(白)ブンチョウ
サクラ(桜)ブンチョウ
[性質]
ブンチョウは気が強く好き嫌いのはっきりしている鳥で、つがいや他の鳥と一緒のカゴで飼う場合はケンカをすることがあるので気をつけましょう。ケンカをするようであれば、別々のカゴで飼うほうがよいでしょう。
丈夫で比較的寒さにも強い鳥です。
水浴の大好きな鳥なので、水浴用の大きめの水入れを用意し、毎日きれいな水を与えてあげましょう。
人によく慣れるので手乗りにできます。
[オスとメスの見分け方]
あまりはっきりとした違いがなく区別が難しいといわれています。
くちばし
オス…太くて紅色が濃い。
メス…オスと比べて小さく紅色が薄い。
目のまわり
オス…紅色で完全に輪になっている。
メス…オスよりも薄く、どこかで1ヶ所切れていて完全な輪になっていない。
オスは発情すると、止まり木の上で “ピョ、ピョ、チェッ、チェッ” とダンスをしながらさえずるのが特徴です。
[気をつけよう]…こんな様子が見られたら、早めに治療を受けましょう!
①全身の羽毛を膨らませる。
②食欲がない。やせてきた。
③くちばしの異常 : くちばしの色で体調が分かるので普段と違うときは注意してください。
④かゆがる。
⑤口を開けて呼吸する。
⑥腹部が膨れている。
⑦コブ、イボができている。
⑧翼を垂らしている。脚が動かない。
⑨フンが軟らかい。下痢。血が混ざっている。
⑩肛門付近の異常。汚れ、はれ、腸が出ている。
[小鳥に多い病気]
①トリコモナス症 : 呼吸困難、下痢、元気・食欲がない。
トリコモナスという小さい虫の仲間による病気。ハトやカナリヤ、小型のインコに多く、うつる病気です。
②卵づまり : お尻のあたりが膨らんでいる。
カルシウム不足などで卵の殻が軟らかすぎたり、卵の大きさに異常があると自然に卵を産み出せないことがあります。下腹部が大きく膨らみ、触ってみると卵に触れることができます。母鳥は疲れ、急に元気を失うこともあります。
③外部寄生虫 : シラミやダニなど注意。
特にカイセンによる皮膚病が多く、その場合は皮膚がカサカサし、かゆみの為、顔をカゴにこすりつける動作が見られることが多いです。皮膚だけでなく嘴や肢の変形が見られることもあります。
※知っておかなければいけない病気
オウム病 : 元気・食欲がない。
クラミジアというウイルスのようなものによる病気で、オウム・インコ類、フィンチ類、ハト、野鳥などの鳥類にうつる病気です。鳥以外でもうつり、人にもうつるので注意が必要です。人にうつった場合は、肺炎や気管支炎などを起こし、咳が出たり呼吸が苦しくなり死に至ることもあります。